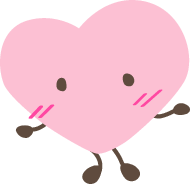早期発見と的確な診断のために、精神科において行う認知症検査についてのコラムです。
認知症は、認知機能の低下を特徴とする病気であり、単に個人の問題とは言い切れない社会全体の問題といえます。平均寿命が延び、高齢者の認知症患者は増加傾向にあります。また、65歳未満で発症する若年性認知症は、男性に多い傾向にあります。
認知症は早期に発見し、適切な治療やケアを行うことが何より重要です。本記事では、精神科専門医による認知症検査の重要性と手法について詳しくご説明します。
認知症の特徴と症状
認知症は、記憶力や判断力、言語理解などの認知機能の低下が特徴です。例えば、初期段階では、日常生活での小さなミスや物忘れが増えることがあります。また、予定の記憶が曖昧になったり、鍵や財布の置き場所を忘れたりすることがあります。さらに進行すると、時間や場所の混乱が生じ、迷子になる、身近な人の顔や名前が思い出せなくなるなど、日常生活において大きな問題が生じます。
認知症検査の目的と利点
認知症検査の主な目的は、患者さんの認知機能を評価し、早期にの認知症の兆候を発見することです。
具体例としては、患者さんが自分の予定や医師の指示を正確に覚えているかどうかを評価することが挙げられます。また、患者さんの記憶力、注意力、計算力、言語能力、判断力などを評価するテストも行われます。
認知症の特徴や症状は個人によって異なりますが、早期の発見と適切な対応がその後の治療や日常生活に大きく影響します。
検査結果に基づいて適切な治療やケアを行うことで、認知症の進行を遅らせることができます。また適切なサポートを提供することで、患者さんの健康と生活の質を向上させることもできます。
認知症検査は、認知症の診断を下すための唯一の方法ではありませんが、早期発見に役立つ重要なツールです。認知症の兆候が気になる方は、早めに医師に相談することをお勧めします。
主要な認知症検査手法の紹介
一般的によく使用される認知症検査手法には「長谷川式認知症スケール」と「MMSE」があります。
「長谷川式認知症スケール」は、
精神科医の長谷川和夫先生によって開発された認知機能検査です。医師が効率的かつ公平に認知機能の低下を診断するために1974年に開発され、1991年に一部改定されました。
この検査は30点満点で、20点以下だった場合、認知症の疑いが高いと言われますが、診断結果はあくまでも参考です。このテストの点数が悪かったからといって、「認知症」と診断されるものではありません。気になる場合は、病院に行って検査・診断をおすすめします。
長谷川式認知症スケールは、9つの評価項目から構成されています。
例えば、
– 年齢はいくつですか?
– 今日は何年ですか?何月ですか?何日ですか?何曜日ですか?
– 私たちが今いるところはどこですか?
– これから言う3つの言葉を言ってみてください。①桜、猫、電車または②梅、犬、自動車。後でまた聞きますのでよく覚えておいてください。
– 100から7を順番に引いてください。それからまた7を引くと?
このように、長谷川式認知症スケールは、認知機能の低下が認められるか判定するために行う検査になります。
「MMSE検査」
認知症が疑われるときに行われる神経心理検査のひとつです。1975年にアメリカで誕生し、国際的に用いられている検査で、2006年に日本語版が完成しました。
この検査は、認知機能の低下を点数で客観的に計測することができる、世界各国で用いられている検査方法です。短時間で簡潔に行える検査で、低下している認知機能の種類や低下度合いを客観的に確認できます。ただし、あくまでもスクリーニング検査なので、MMSEの結果だけで認知症の診断はできません。
認知症の診断は、上記の検査だけでなく、MRI・CTによる脳検査、本人や家族からの聞き取り、鑑別診断なども行った上で総合的に判断します
最後に
認知症は早期の発見と適切な対応が重要です。精神科専門医による認知症検査は、その第一歩となります。
物忘れが増えたり、仕事でミスが多くなったり、何かしら日常生活に支障があるときは、お早めにご相談下さい。
※公開/更新日: 2023年6月10日 14:38